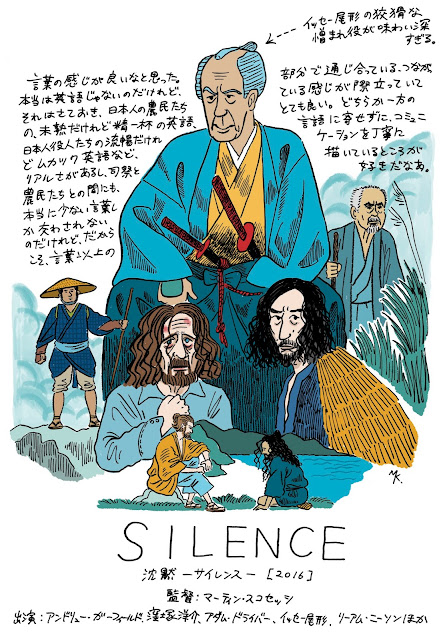インターネットの楽しいところはなんといっても外国のひととやり取りできるところだ。と言っても今までそんなに何人もやり取りしたわけではないけれど、スコットランドのイラストレーターの女の人とは高校以来ちょくちょくやり取りをしている。高校時代に閲覧範囲がぐっと広がったときに彼女のブログを見つけて、ミリペンによる繊細なタッチと、しっかりした画力に裏付けられた絵が素晴らしかったので、つたない英語で感想を書いてメールしたのが最初だったと思う。以来インターネットの過剰な情報量に圧倒されてたびたび興味の対象を変えながらも、それでもなんとなく安定して使用できるSNSの登場で彼女とのやり取りを続けられている。インスタグラムではスコットランドの織部色の山々の写真を観ることができて、あちこち岩が散在している霧のかかった草原は、まさにホグワーツ城を目指したホグワーツ特急が煙を吐きながら通っていたような景色で、同時にシャーロック・ホームズが魔犬との闘いを繰り広げていそうな景色でもあった。あの環境があのかっこいい絵のタッチを生むんだろうか。繊細さと硬さが同居して、ドライで古風、けれどそこまで無愛想でもないあのタッチ。
先日、珍しくフェイスブックのメッセンジャーに彼女からメッセージが届いた。たまごっちが欲しいが手に入らないのでそっちで売っていないかなという内容。もちろん売っているので、アマゾンのリンクを貼って返信した。オリジナルが欲しいということだったけど、ガチの96年製よりも最近出た復刻版の方が安いし新しいよ。復刻版を探してたから全然オーケー。
さて購入方法である。日本のアマゾンにあったわけだが、これは外国のひとも購入できるんだろうか。こっちのひとでもアメリカのアマゾンを利用している人はいるけれど、アカウントを別に作ったりしているんだっけ。なんだかよくわからない。そんなことも知らないのかと言われそうだが、ぼくはなんだかんだネットに疎く、外国のものを買うのはもちろん、通販だって実のところよくわかっていないところが多い(我が家が使うアマゾンのアカウントは専ら妻のもの)。方法はいくらでもあるんだろうけれど、それを英語で説明するのも面倒くさいし、ある程度は向こうだって調べていることだろう。代理購入してペイパルかなにかでお金のやり取りしたっていいけれど、それも面倒くさい。ていうか、そんなに高いものじゃないし、プレゼントしちゃえばいいじゃん。それに彼女、最近入院して脚の手術をしていたから、一応お見舞いになる。
というわけで、よかったら買って贈りますよと言ったら、大変喜んでいた。それならこちらからもなにか贈るよ、UKのものでなにか欲しいものある?
UKで欲しいもの。なんだろう。すぐに思いつかず妻に聞いてみると、例によってロンドン土産のコーギーのぬいぐるみとか言う。スコットランドに住んでるひとにロンドン土産を頼むのはどうなのか。と言ってぼくがぼんやり思いついたシャーロック・ホームズのグッズとかも同じことであった。じゃあハリー・ポッターの何かとか、ドクター・フーの何かとか?何かとはなんだろう。そしてぼくはドクター・フーを一度もちゃんと観たことがない……って結局オタクなグッズしか思い浮かばないので、なにかUKっぽいものを!とお任せでお願いした。と、さっきからスムーズに英語のやり取りができているように見えるが、実際は返信するたびにネット検索と翻訳アプリを使いまくって一文ずつひいひい言いながら書いていた。言いたいことを言いたいニュアンスのまま伝えようとするのが、一言で済むものでも大変。
アマゾンからたまごっちが届いたが、小さな物なので箱の中にずいぶんなスペースが余っている。そこで妻のアイデアでスーパーでうまい棒をたくさん買ってきてスペースに詰めた。こうやってプレゼント贈るひとがネットにいたらしい。さらに原宿のキディランドに行ってピカチュウとかハローキティの食玩を物色する。スコットランドの彼女はこのあたりの日本製キャラクターものも好きなようだったから、気に入らないということはないだろう。でもあまり日本感出すのは趣味じゃないしダサいのでそのあたりにしておく。
かくして箱の中はほどよくぎゅうぎゅうになった。手紙を書いて箱をテープで頑丈に封印する。この手紙ももちろんコンピューターに助けられながら書いた。文法的に正しいのか、体裁が整っているかは二の次で、とりあえず伝えたいことを、悪い意味に取られることのないように書いた、つもり。ぼくの場合はひとまずそれで十分だと思っている。それでもこれまで特に誤解や問題なくやり取りができているのだから、まあまあ伝わるだろうと思う。
郵便局に行って、EMS(海外スピード郵便)の伝票を書く。自分で外国に手紙も出したことがないし、荷物も初めてだ。個数とかそれぞれの重さとか値段とかの記入欄があって少し焦ったが、ひとつずつ計算して書いていく。
「『Toys』って、具体的になんですか?」
郵便局のひとに聞かれたので、
「えーと、プラスチックでー」
我ながらひどい答えだった。だいたいのおもちゃはプラスチックだ。積み木とかじゃない限り。
「なんか電池入れて動くとか?」
「動くといえば動きます」
「どんな電池?ものによっては送れないかもしれないんですよ」
「えーと、ボタン電池でー」
「ボタン電池、それなら大丈夫かな。それでどういうふうに遊ぶものですか?このあたり詳しく聞いといたほうがいいんで」
ええい、言ってしまえ。
「ていうか、たまごっちなんですよ」
「ああ、たまごっちねえ。たまごっちって英語でなんて言うのかしらね」
と同僚の女性に聞く。
「さあ、『タマゴッチ』じゃないの?」
「そう書いとくしかないのかなあ」
「エレクトロニクス・ゲームとかですかね」
とぼく。適当である。
「じゃあ、ここんとこにそう書いといてもらえます?」
iPhoneでエレクトロニクスのスペルを調べるぼく。すると背後で自動ドアがスライドして、歩み寄ってくる気配。妻だった。仕事の帰りとちょうどタイミングが合ったので郵便局にいると伝えていたのだった。
「書けた?」
伝票を覗き込む妻。
現状を説明するのが面倒くさいので適当に「うん」と言っておく。
「電池が何個入ってるかわかります?」
と郵便屋さん。
「一個くらいかと……」
「じゃあボタン電池が入ってるよってことも小さく書いといてください」
んー、ボタン電池って英語でなんて言うのかな。すかさず手のひらの中にあるグーグルに「ボタン電池 英語」と打つと「Button battery」と出たのでそのまま書こうとする。すると妻が、
「ちょっとちょっと、Coin Batteryだよ。ボタンって打ったらそりゃButtonって出るでしょ」
ええい、うるさーい!
そんなことはわかってる!わかっているが焦っているのだ。
郵便局員ふたりと妻が見守る中こうしてぼくは初めて海外宛ての伝票を書き上げた。
ああ、これでぼくはこの郵便局では「たまごっちのひと」となってしまうんだろうなあ。仕事の請求書を出しに頻繁に使うところなのに。今後は「来たわよたまごっちのひと」とか言われるんだろうか。
本当にあれで問題なく届くのかな。少し不安だがもう出してしまったものは出してしまった。あとは祈るほかない。途端、ぼくの頭には税関でぼくの出したダンボールがとめられる光景が浮かんでくる。赤毛でひょろっとした制服のおじさんが麻薬犬のブルドッグとともに箱を調べ、ボタン電池について調べようとして開封し、開けた途端いっぱいに詰め込まれているうまい棒を見て、そういえばランチがまだだったな、昨日カミさんと喧嘩したから今朝はニシンの燻製を食べ損ねていたんだった。こいつは日本のお菓子かな?なんだかうまそうだ。よう、ジャック、おまえも食うか?とブルドッグに尋ねるとブルドッグはうれしそうに短いしっぽを振り、そうこうするうちに他の職員も群がってきて珍しい日本のスナック菓子を奪い合い、うまい棒の、チートス並みにやみつきになる味に夢中になり、ボタン電池のことも忘れて仕事そっちのけで皆で指先をオレンジ色にしながらうまい棒を食べるという光景が浮かんだ。もちろんぼくの空想で、連合王国の税関がそんなんなわけがない。
無事に届きますようにと思うばかりだ。